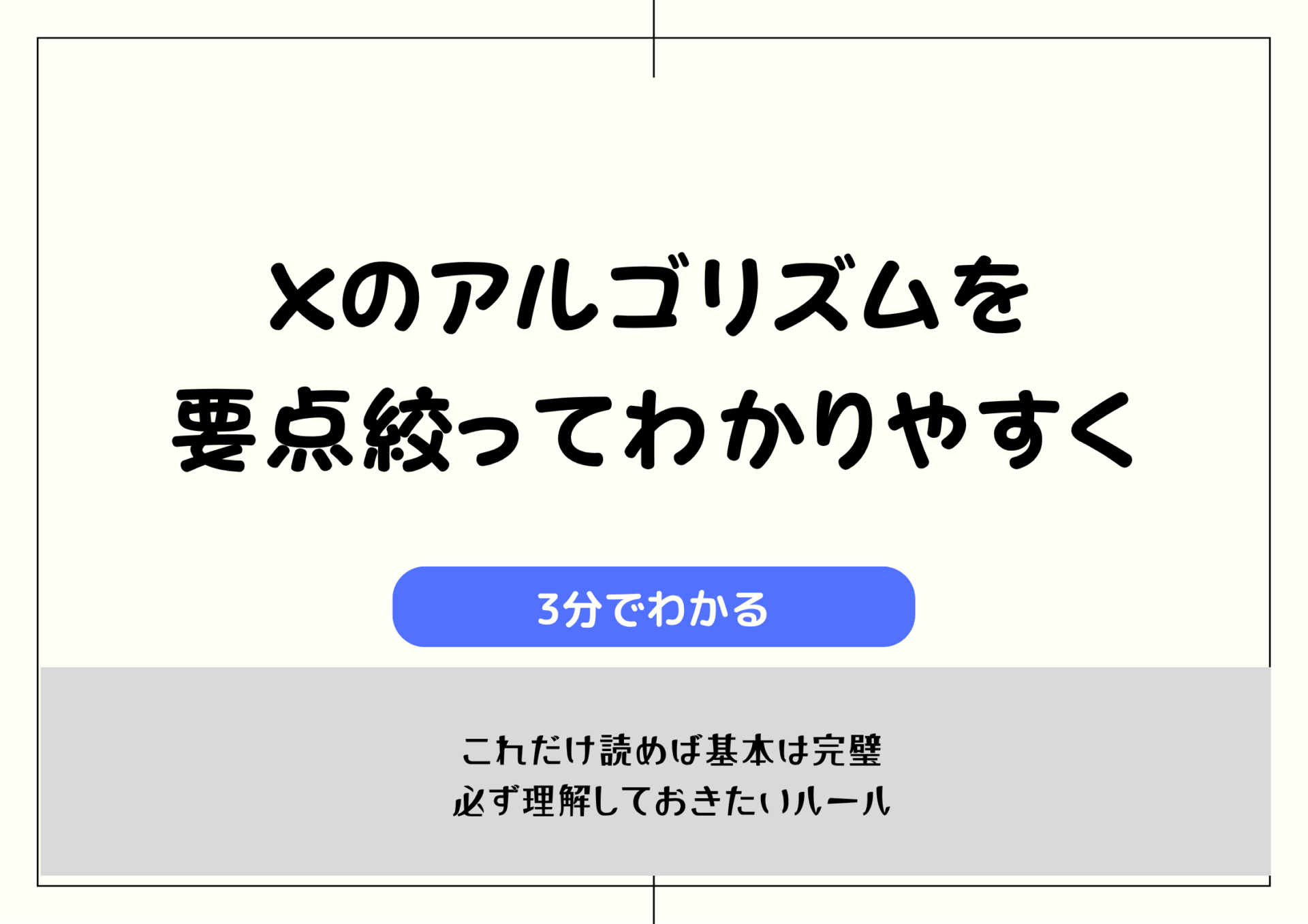Xのアルゴリズム理解してますか?
アルゴリズムを理解しない運用は「ギャンブル」
「なんとなく良い投稿をすれば、いつか誰かが見つけてくれるはず」
このような感覚的な運用を続けている限り
あなたのアカウントが劇的に伸びることはありません。
なぜなら、それは「ルールを知らずにチェスを指す」ようなものだからです。
X運用にはアルゴリズムという明確な「ルール」が存在します。
アルゴリズムの本質:「ユーザーの滞在時間最大化」
アルゴリズムの本質は極めてシンプルです。
X社の売上の約90%弱が広告収益であり
その収益を最大化するためには、ユーザーに1秒でも長くXに滞在してもらい
広告に接触する機会を増やす必要があります。
つまり、X社に優遇されるアカウントとは
ユーザーをXに長く滞在させることができるポスト(=良い投稿)を
コンスタントに生み出すアカウントなのです。
長文投稿、動画、画像、リプライ欄での議論など
Xに実装されている多くの機能は、すべてこの「滞在時間」を伸ばすために設計されています。
アルゴリズムを攻略する3つの要素
【要素1】滞在時間
最も本質的で、すべての戦術の土台となるのが「滞在時間」です。
アルゴリズムは、個々のポストが
「ユーザーの時間をどれだけ奪うことができたか」を計測しており
その時間が長いほど「価値のあるコンテンツ」だと判断し
より多くのインプレッションを与えます。
ここで重要なのは、「いいね」の数ではなく
「詳細クリック」や「プロフィールクリック」といった
ユーザーがより多くの時間を費やした証拠となる数字です。
【要素2】関心度(グルーピング)
Xのアルゴリズムは、個々のアカウントを
その発信内容や交流関係に基づき
約14万5000あるとされるコミュニティ(ジャンル)のいずれかに自動的に分類しています。
そして、そのコミュニティ内で人気のあるポストを
「関心度が高い」と判断し、同じコミュニティに属する他のユーザーに優先的に表示させます。
これこそが、「発信軸の統一」がなぜ重要なのかという技術的な理由です。
発信内容がブレると、アルゴリズムがアカウントを正しく「ジャンル認定」できず
結果として誰にも興味を持たれない中途半端な層にしかポストが届かなくなってしまいます。
【要素3】親密度
第3の要素は、アカウント間の関係性の強さを示す「親密度」です。
アルゴリズムは、「誰をフォローしているか」
「誰と頻繁に交流(いいね・リプライ)しているか」という2つのアクションを基に
アカウント間の「親密度スコア」を常に計算しています。
そして、あるユーザーと親密度が高い別のアカウントのポストは
そのユーザーのおすすめタイムラインに表示されやすくなります。
見るべき指標の優先順位
多くの人が「いいね」の数を追いかけますが
アルゴリズム上で本当に重要なのは以下の順番です
- 詳細クリック数(続きが気になってクリック)
- プロフィールクリック数(この人に興味を持った証拠)
- リプライ数(エンゲージメントの証拠)
- リポスト数(価値を感じた証拠)
- いいね数(最も軽い反応)
「いいね」は最も軽い反応であり
アルゴリズムの評価も最も低いのです。
戦略的な交流でアルゴリズムを味方につける
現在のXは、数年前と比べてグルーピングの精度が向上しています。
つまり、あなたのポストが届く場所が、届けたい場所により届きやすくなっているのです。
これを味方につけるためには
「誰と交流するか」が極めて重要です。
自身のジャンルにおける「村長(=トップインフルエンサー)」を3名
「有力者(=中堅インフルエンサー)」を5名
「村人(=同レベルの仲間)」を10名リストアップしてください。
サロン内であればフォロワー1000人以下の人は
共にがんばる「金の卵」のメンバーと仲良くするといいでしょう!
あとは、同じ発信軸のグループの方がお薦めです!
そして、毎日その中の誰かと質の高い交流を行うことで
アルゴリズムに対して「自分がどの村に所属したいのか」を強烈にアピールするのです。
感覚的な運用からの完全脱却
アルゴリズムは常に進化し続けています。
昨日まで通用していた手法が、今日には効果を失っている可能性があります。
だからこそ、小手先のテクニックではなく
この3つの要素という「普遍的な本質」を理解することが重要なのです。
この本質を理解すれば、すべての行動指針は自ずと定まります。
「このポストはユーザーの時間を奪うものではないか?」
「このポストはユーザーに、もっと知りたい、もっと見たいと思わせ、Xの中に留まらせる力があるか?」
これこそが、アカウント運用の質を決定づける問いなのです。
感覚に頼らず、アルゴリズムという「ルール」を味方につけて
確実に成果を出していきましょう。